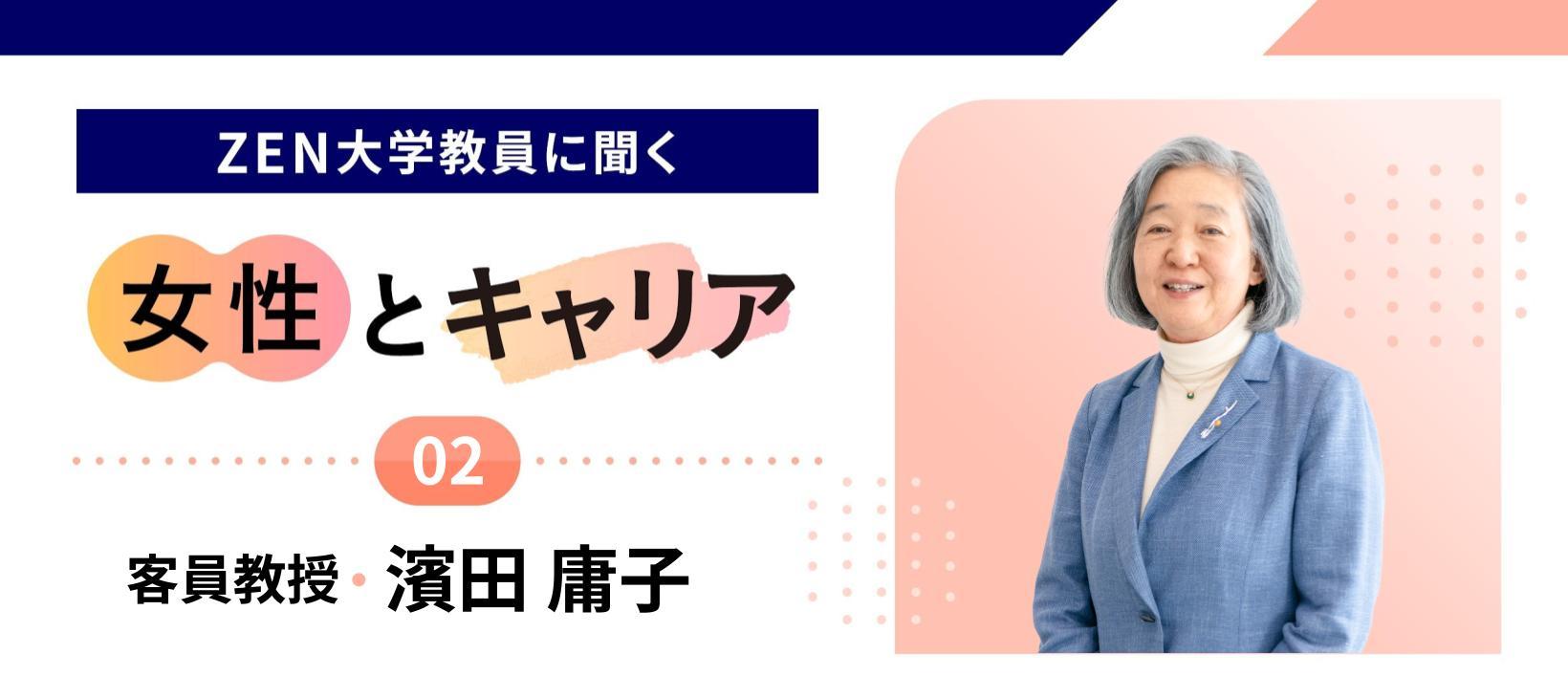ZEN大学で開講される多彩な授業では、内容もさることながら教員自身のキャリア形成や活躍の幅広さも、学生の皆さんが将来を考える上で参考になるはずです。特に、出産や育児などのライフイベントとキャリアのバランスに悩むことが多い女性にとって、教壇に立つ女性教員のさまざまな生き方を知ることは、自分らしい学び方や働き方を選択するためのヒントとなるのでは。教員へのインタビューを通して応援のメッセージを贈ります。
今回は「こころの成り立ちとメンタルヘルス」の授業をご担当いただく濱田庸子氏にインタビューしました。
――経歴を教えてください。
内部進学で慶應義塾大学医学部に進学し、卒業直前に結婚しました。卒業後は精神科専門病院に勤務する傍らで精神分析的精神療法を勉強し、この間に第1子の出産・育児も経験しました。卒後10年目からは、医療現場を離れ大学の保健センターに移り、講義と学生相談をするように。夫の留学に帯同してアメリカにも滞在し、帰国後に第2子を出産。その直後に前任校に異動し、約30年勤め定年退職しました。現在は非常勤の医師として、臨床や精神保健相談に携わっています。

――精神科医というキャリアを選んだ背景
私が学生の頃はまだ、男女雇用機会均等法が施行される前。男社会の中で会社員になっても自分らしく働けないのではないかと考え、進学先に医学部を選びました。しかし「女性は結婚したらやめるので育成しにくい」と面と向かって言われたくらい、医師の世界も男性中心でした。
思春期に社会や大人への不信感を抱いた経験があり、そんな自分の心の変化を不思議に思ったことから精神分析に興味を持ち、精神科医になることを考え始めました。ただ当時、精神科医には「精神病の人を管理する大変な仕事」というイメージが強く、「女性がする仕事ではない」と止められたことも。それでも、外来を見学した際に出会った先生の「女性にしかわからないことがあるよ」という言葉が背中を押してくれました。その言葉どおり、病院勤務や研究を続ける中で、妊娠・出産や子育てなど、女性ならではの視点を必要とされる場面は多かったですね。
――医師として研究者として、そして母親として
臨床では、産後うつや子どもの発達障害などの相談・治療を行っています。一方で、「乳幼児精神医学」という新領域に関する研究や出版、乳幼児の表情写真を通して養育者の情緒反応を測定するツール「IFEEL Pictures」日本版の開発などに携わり、治療と研究を繋げて実践してきました。自分自身の出産・育児の経験を通して、学んできたことを体感しながら理解を深められました。
第1子出産後は郊外の精神科病院で週4日時短勤務、研究日を1日もらって、マイペースに働きました。内科医の夫は忙しく、家事は私が引き受けていました。当時は思うように研究できない葛藤もありましたが、乳幼児精神医学の勉強から乳幼児期の大切さを知り、育児を楽しむことができるようになりました。そしてこの経験が、私の研究の基盤になりました。
現代は男性の育休や育児参加が増え、家事育児の分担に関する固定概念は変わってきていると感じます。しかし時代が変わっても乳幼児期の大切さは変わりません。産後うつの相談に来る方には「子育ての時間を楽しみなさい」と伝え、支援しています。赤ちゃんは生後3ヶ月の間に養育者と脳の同期を行い、情緒的なコミュニケーションを学ぶのです。最近は、矯正施設で非行をした子どもたちを診ているのですが、幼い頃の虐待やトラウマが関係していることが多く、幼少期がいかに大切な時期であるかを再認識しています。
――「こころの成り立ちとメンタルヘルス」はどんな授業?
少人数でリアルタイムのオンライン授業を行い、さまざまな心の問題について理論の講義および履修者のグループ・ディスカッションをします。家族や友人には話せなかったことや言葉にならないような不安を他者と共有する経験は貴重です。共感者がいることへの安らぎ、他者の話から気づきを得ることなどに繋がり、自己・他者理解を深めることができます。心の問題や対人援助職に興味がある方のほか、人工知能の研究にも役立つかもしれません。

――学生へのメッセージ
学生時代は仲間と研究グループを作って、ウイルスなどの勉強もしましたが、やっぱり自分の専門はこれだ!と思えたのが精神医学でした。皆さんも、自分に制限を設けず興味のあることはやってみてほしいです。回り道をしても最終的に本当に好きなものにたどり着くことが大切。回り道の経験はどこかで必ず活きてきます。女性でも男性でも、自分の「良さ」を認めて活かすことができる環境に身を置いてほしいと思います。