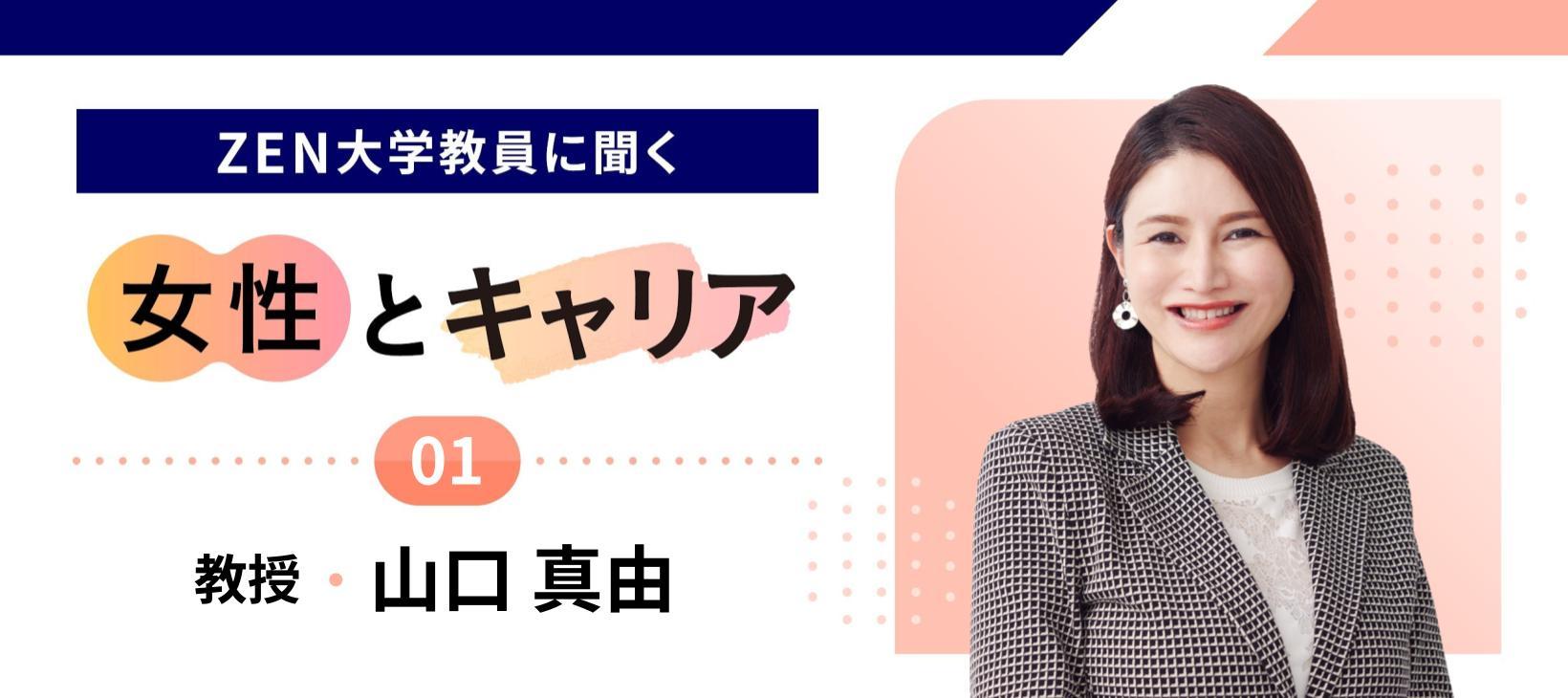ZEN大学で開講される多彩な授業では、内容もさることながら教員自身のキャリア形成や活躍の幅広さも学生の皆さんが将来を考える上で参考になるはずです。特に、出産や育児などのライフイベントとキャリアのバランスに悩むことが多い女性にとって、教壇に立つ女性教員のさまざまな生き方を知ることは、自分らしい学び方や働き方を選択するためのヒントとなるのではないでしょうか。教員へのインタビューを通して応援のメッセージを贈ります。
今回は「法学Ⅰ」の授業をご担当いただく山口真由氏にインタビューしました。
――経歴を教えてください。
東京大学法学部を卒業後、財務省に入省し主税局にて従事しました。その後退職し、弁護士事務所を経てハーバード大学ロースクールへ留学。帰国後、東京大学大学院法学政治学研究科総合法政専攻博士課程を修了し、現在は信州大学で教鞭をとる傍ら、コメンテーターとしてテレビ番組などへ出演しています。
――幼少期からのキャリア観とその変化
両親共に医師という環境で育ち、国家資格を持つことや結婚・出産してからも働く母の姿は私の進路に影響を与えていると思います。男女が同じように出世することが難しかった母の時代において、資格は女性の武器という考えがあり、私が資格試験に興味を持つきっかけになりました。
財務省に入った頃にも、そこまで露骨ではなくともジェンダーにおける「ガラスの天井・壁」は確実にありました。勉強では男性にも負けたことがなかった私は仕事も同じようにできると思っていたのですが、ハードワークをこなせず初めての挫折を経験。弁護士事務所に移ってからも自分の不甲斐なさを感じると同時に、女性が中枢ポストに行きにくい現実を目の当たりにしました。
そんなキャリアを華麗に塗り替えるべく、留学と婚約を決意。しかし、留学中になんと婚約破棄に!帰国してからは婚活に奔走するもうまくいかず……。成績優秀でやってきた私は「人生を選ぶ側の人間」だと信じていたのですが、この時初めて「選ばれるのを待つ側」にいることに気づき愕然としました。漠然と高学歴高収入の相手と結婚するはずだと思っていたのに、そういった人は私を求めていなかったのです。

――女性にとって「結婚」「出産」とは
「結婚は絶対するもの」という思い込みが私を苦しめていました。今の時代、結婚は人生の選択肢のひとつ。結婚しなくても子どもをもうける手段だってあります。子どもがいない人生を選択する方もいます。自分の人生はこうじゃなきゃいけないという思い込みを捨ててからは自分のしなやかさに気づくことができ、荒波にもまれるうちに見栄がそぎ落とされ、過去の自分をバネにできるようになったのです。財務省時代の質素な暮らしも、「これさえあれば私は生きていける」というミニマムな生活水準として心に刻まれていますし、かつての婚約者に書いた手紙を読み返してクスッと笑えるようにもなりました(笑)
男性とは逆で女性は学歴が高いほど選ばれにくくなるという海外の研究結果もありますが、女性が勉強してチャレンジを重ねていくことは素晴らしいこと。何事も「自分一人でも生きていく力を身につける」という気持ちで臨むことが大事かもしれませんね。
また、子どもを持つか持たないか、いくつで産むかなど選択は自由ですが、女性は体のことを事前に理解しておくことも大切です。私は長い不妊治療の末、39歳で出産しました。卵巣年齢を診てもらったら50歳と言われ慌てて卵子凍結をしたことも。今は医療技術が進み高齢出産も増えていますが、お金も時間もかかるのは事実。自分が何を大切にして生きていくのかを明確にして、キャリアプランを早めに立てておくことをおすすめします。
――現在、子育てとキャリアの両立は
仕事と家事と育児、ジャグリングのような毎日ですが、新しいチャレンジを楽しんでいます。産後1ヶ月ほどで仕事に復帰しましたが、24時間気を張り続ける子育てから離れて、知的な会話ができる職場に行くことは癒しにもなっています。一方で、子どもの体調などに合わせてリモートをお願いするなど柔軟な働き方を切り拓こうという意志が生まれました。仕事と子育て両方があるからこその良さがありますね。また、私が楽しく働く母に誇りを感じていたように、自分が働いていることで子どもに見せてあげられる世界は広くなるのではないかと信じています。
――学生へのメッセージ
ZEN大学は実社会と教育を連結させようという強い意志のある大学です。最先端の環境の中、多様なバックグラウンドを持つ教職員と出会い、様々な働き方を知れる現場体験型プログラムに参加できるので、現実に即してキャリアプランを考えやすいと思います。私が担当する「法学Ⅰ」でも、社会に出た時に役立つ内容を教えたいと考えています。例えば、賃貸マンションを借りる際の契約、就職先での待遇、SNSでの誹謗中傷など身近な場面に存在する法についてわかりやすくお伝えします。大学で学ぶことが社会できちんと評価されることを願いつつ、私も皆さんから刺激をもらえることを楽しみにしています。